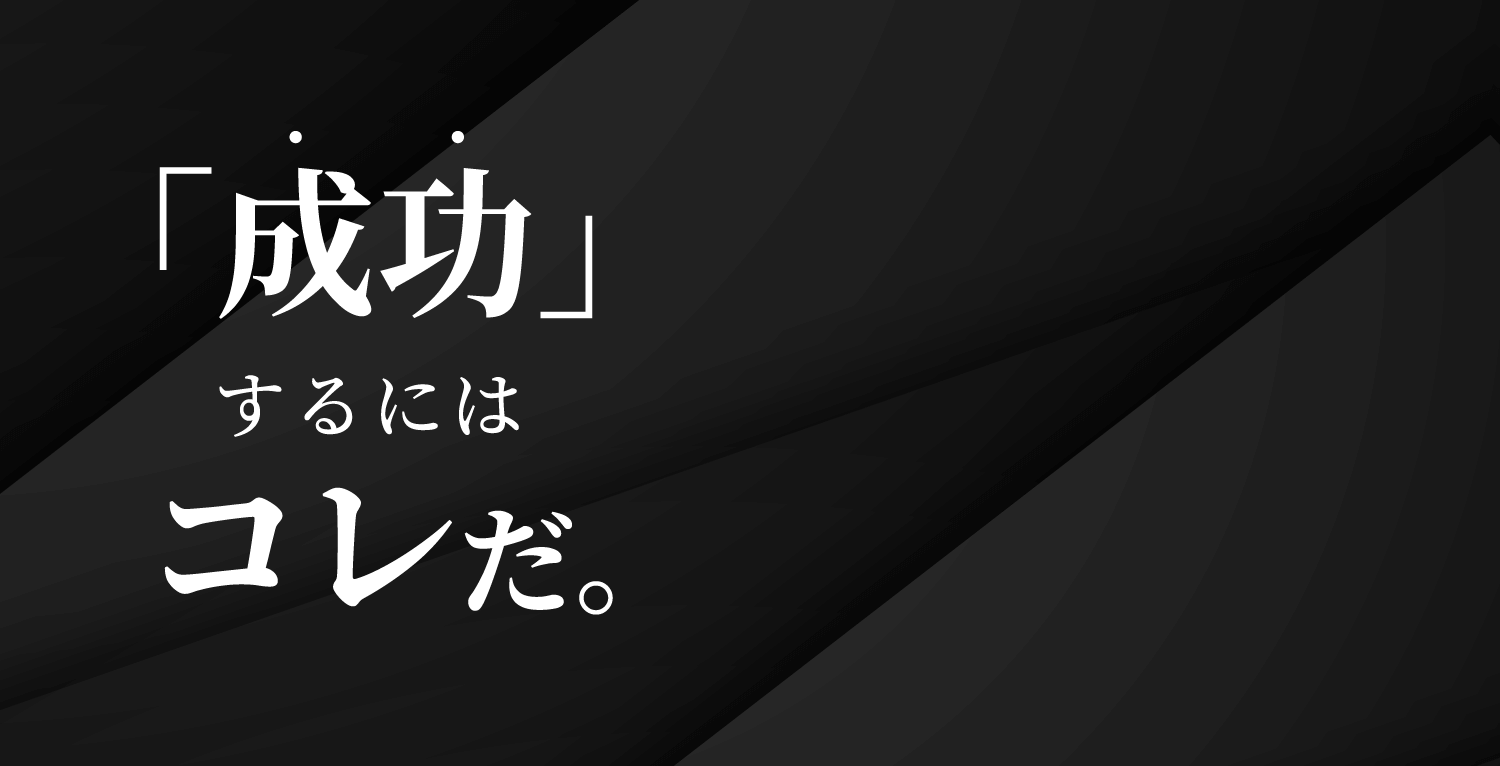就労支援事業の立ち上げはなぜ難しい?準備段階で押さえたい要点を徹底解説
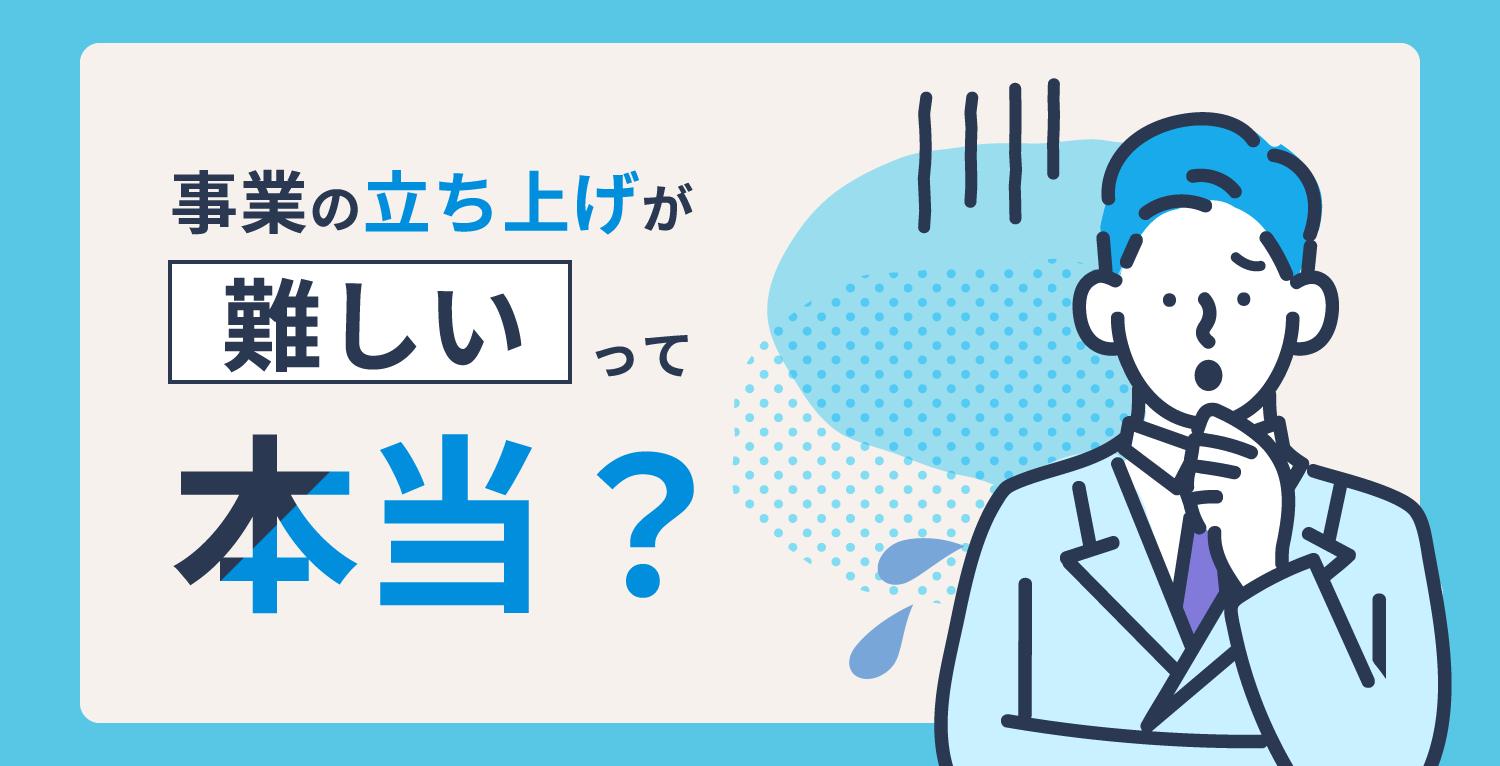

就労支援事業の立ち上げが難しそうで、少し自信がなくなってきました。

一つひとつ準備を進めていけば、着実に形にすることができます。一緒に準備のポイントを確認していきましょう。
「福祉の現場に貢献したい」「社会課題の解決に関わるビジネスがしたい」と考え、就労支援事業に興味を持つ方は増えています。
しかし実際には、「立ち上げのハードルが高そう」「制度が複雑で何から手をつけて良いか分からない」といった声も多く、準備段階でつまずくケースが少なくありません。
ここでは、就労継続支援A型・B型事業所を立ち上げる際に多くの方が直面する課題や、その対策について詳しく解説します。
失敗を避けるために押さえておきたいポイントを理解し、安心してスタートラインに立てるよう、ぜひ参考にしてください。
結論:制度理解・人材確保・行政対応が成功のカギ
就労支援事業の立ち上げが難しい最大の理由は、「制度が複雑で、専門性が求められる点」にあります。 加えて、専門スタッフの確保や、自治体との調整、事業計画の立案など、多岐にわたる準備が必要です。
裏を返せば、以下の3つのポイントを押さえることで、未経験者であっても着実に立ち上げを進めることができます。
・制度を正しく理解すること
・経験者の力を借りること
・地域の実情に合わせた計画を立てること
これらのポイントを押さえることで、未経験者でも立ち上げは可能です。
特にフランチャイズに加盟することで、制度理解や採用・広報・収支計画に至るまで、立ち上げに必要なノウハウや支援体制を網羅的に得られる点は、大きな安心材料となります。
立ち上げに必要な準備とハードル
就労支援事業の立ち上げには、制度や書類だけでなく、地域性や運営まで見据えた準備が求められます。つまずきやすいポイントを押さえて、成功につなげましょう。
就労支援事業における「計画力」の重要性
就労支援事業の立ち上げでは、単に必要書類や制度を整えるだけでは不十分です。地域ニーズを正確に捉えたサービス構築や、持続可能な事業モデルを描く「計画力」が問われます。
その中でも特に重要なのが、以下の観点です。
・地域の障がい者人口、相談支援事業所、競合事業所の状況を踏まえた利用者獲得戦略
・収益性と支援の質を両立するためのサービス設計
・立ち上げ後の成長フェーズを見据えた組織づくり・人材育成
こうした長期視点での準備が不足していると、開設後に「就労支援サービスを利用する方(以下、利用者)が集まらない」「人材が定着しない」「黒字化の見通しが立たない」といった課題に直面しやすくなります。

立ち上げ時に特に注意すべき4つの壁
就労支援事業を始める際、特に注意すべき大きな壁が4つあります。 これらは多くの事業者が直面する共通課題であり、事前に把握し対策を練ることが成功の鍵となります。
1.制度の複雑さと情報の少なさ
就労支援事業は、障害者総合支援法に基づく指定事業であり、運営には報酬基準・配置基準など、多くの法令知識を必要とします。
特に報酬制度には多くの加算項目が存在し、それぞれに取得条件と届出が必要です。
加えて、自治体ごとに微細な運用ルールの差異もあり、「制度は知っていても地域事情でつまずく」ケースも多いのです。
2.専門人材の確保が必須
就労支援事業には、国家資格保持者や一定の経験年数を持つ人材が必要とされます(例:サービス管理責任者は障害福祉経験8年以上など)。
地域によっては対象人材が少なく、採用活動が長期化することも。さらに、給与水準や職場環境次第で離職率が高まる可能性もあるため、長期的な人事戦略が求められます。
3.行政とのやり取りが煩雑
事業指定のためには、各自治体の障がい福祉担当窓口との事前協議、事業所の物理的条件の確認(消防法、建築基準法など)、そして指定申請書類の提出・審査があります。
このプロセスは最低でも3〜6ヶ月以上かかる場合があり、審査の過程で修正・再提出が求められることも。
4.利用者集客・稼働率の壁
事業所は、指定後すぐに利用者が集まるとは限りません。むしろ最初は「認知されていない」状態からのスタートであり、地域の相談支援事業所、医療機関、学校、行政とのネットワーク構築が鍵となります。
特にB型事業所では、稼働率が報酬に直結するため、計画的な集客戦略が必要です。
立ち上げ準備で押さえるべきポイント
立ち上げをスムーズに進めるためには、各ステップごとに必要な手順とポイントを押さえることが重要です。
立ち上げ準備の5つのポイント
ポイント1:地域の行政窓口への相談・情報収集
まず最優先で行いたいのが、開設を検討しているエリアの自治体(福祉課など)への事前相談です。
地域の障がい福祉計画や、ニーズの有無を確認することで、そもそもの設置可否や方向性を判断できます。
「事前協議を飛ばしてスケジュールが大幅に遅れた」という事例もあるため、最初のアクションとして確実に押さえましょう。
ポイント2:人材要件のクリア
職種ごとに必要な資格・経験年数を確認し、採用スケジュールを組み立てましょう。
有資格者の採用に苦戦する場合は、資格取得見込みの人材を採用し、研修とOJTで育成する手段もあります。
また、フランチャイズ本部が人材紹介ネットワークを持っている場合、採用活動の効率化が可能です。
ポイント3:物件選定と施設基準の確認
就労支援事業所には、最低面積・トイレ数・相談室の設置など、施設基準があります。
さらに、バリアフリー・消防設備など、安全性を担保する項目も審査対象となるため、物件探しは専門家の助言を受けながら進めるとスムーズです。

ポイント4:事業計画書・収支計画の作成
収益モデルは、基本報酬+加算報酬+工賃収入で構成されます。
これに人件費、家賃、水光熱費などを加味し、黒字化までの期間を見込んだ収支計画を立てましょう。
また、開業初期は人件費先行となるケースが多いため、開業資金の調達方法(自己資金、融資、助成金等)も検討が必要です。
ポイント5:利用者募集と関係機関への広報
開設が見えてきた段階で、相談支援事業所や医療機関、学校など関係機関への広報をスタートします。
ホームページやパンフレットの作成、見学会の開催、地域イベントへの参加などを通じて、地域に根ざした認知拡大を図りましょう。
また、SNSやGoogleビジネスプロフィールの活用も、情報発信ツールとして効果的です。
まとめ : 成功のカギは「準備力」と「信頼できるパートナー選び」
就労支援事業の立ち上げは、制度理解・人材確保・行政対応・収支設計・集客など、多方面の知識と準備が求められるハードルの高いプロセスです。
しかし、正しい情報を得て、実績あるパートナーやフランチャイズ本部の支援を受けながら進めれば、その難易度は大きく下がります。
「どこから手をつければいいか分からない」という方ほど、早い段階でプロに相談することが、立ち上げ成功への近道です。

準備は大変そうですが、実績のあるパートナーがいればできそうな気がしてきました。

私たちがしっかりサポートしますので、理想の事業所を一緒につくっていきましょう!

 フランチャイズ
フランチャイズ  就労支援
就労支援  運営
運営 
.png)
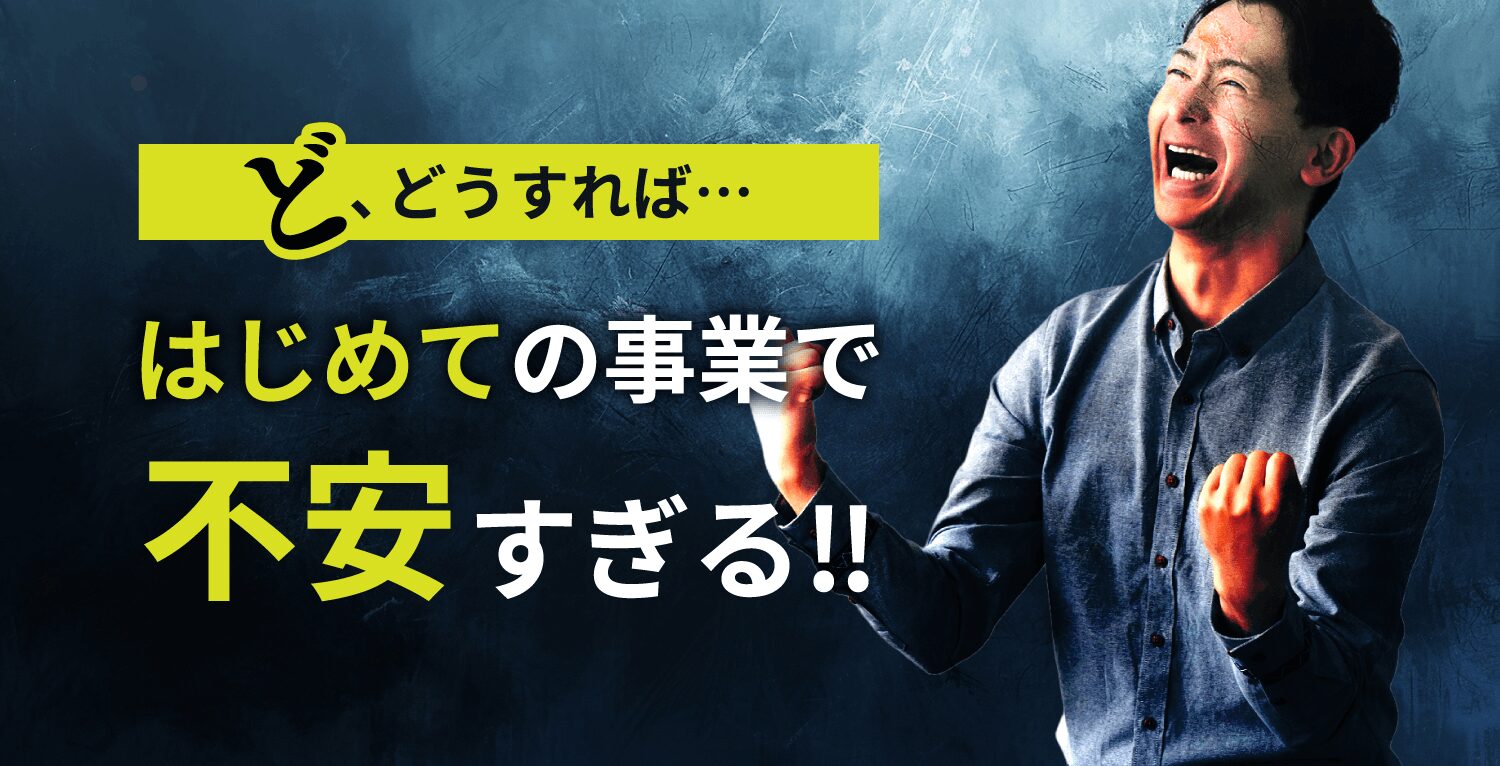

.png)