加算を活かして利益を伸ばすには?制度理解と現場での活用例を詳しく解説
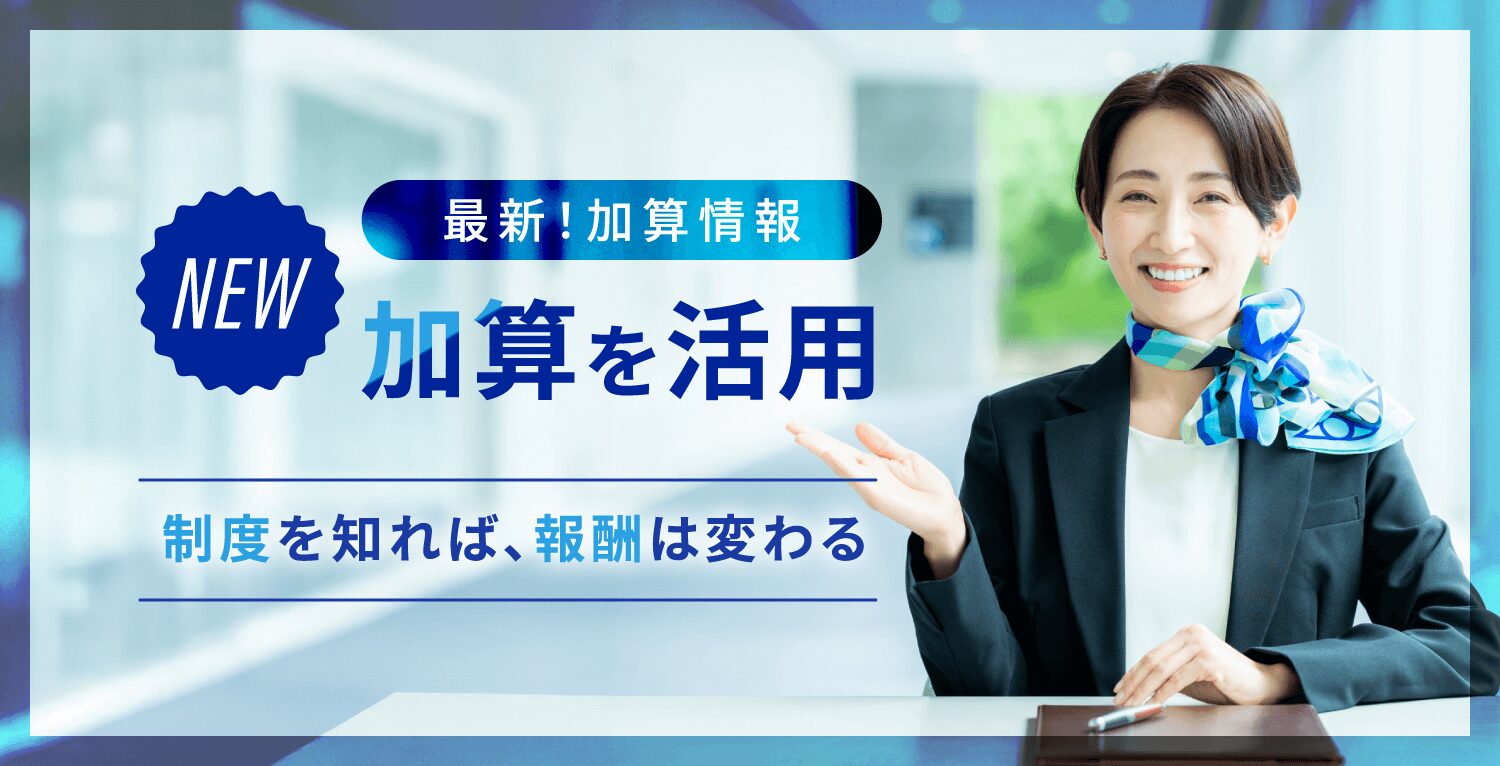

就労継続支援は、加算が重要って聞いたけれど...どういう仕組みなんだろう?

加算は、より質の高い支援や充実した体制を整えた事業所に対して、報酬が上乗せされる仕組みなんです。詳しく見ていきましょう。
就労継続支援A型・B型事業では、支援の質や体制に応じて、基本報酬に上乗せして支給される「加算報酬」が制度上に用意されています。
この加算制度は、単なる収入増を目的としたものではなく、より手厚い支援や専門性のある体制整備を行った事業所が、適切に評価される仕組みです。
たとえば、就労への移行実績、支援記録の充実、専門職の配置などが加算の対象となり、サービスの拡充が報酬にもつながるという好循環が期待できます。
ここでは、加算制度の基本的な考え方から、実際に現場で活用されている代表的な加算の種類や活用方法まで、実践に役立つ視点でわかりやすく解説していきます。
加算制度は「支援の質向上」と「収益の安定化」を両立させる仕組み
加算は単なる報酬アップの手段ではなく、あくまで「より質の高い支援を行うこと」の結果として支給されるものです。つまり、制度をしっかり理解して戦略的に活用することで、就労支援サービスを利用する方(以下、利用者)の支援と事業運営の両面で大きなメリットが得られます。
また、加算要件の多くは記録や運営体制にも関係するため、職員の役割分担や書類管理、業務の流れなどを見直すきっかけにもなります。制度の意図に沿って取り組むことが、結果として経営の安定につながるのです。
目次
なぜ加算の理解と活用が重要なのか?
加算制度は、就労支援事業の運営において「収益性」と「支援の質」を両立させるための大きな柱です。ただし、制度を十分に理解していなければ、本来取得できる加算を逃したり、逆に過剰な業務負担で現場が疲弊したりする可能性もあります。
ここでは、加算制度をどのように捉え、どう活用すべきかという視点から、加算運用の基本的な考え方を整理します。
加算制度は「選択と集中」がポイント
加算には数多くの種類がありますが、すべてを網羅する必要はありません。大切なのは、事業所の規模や利用者の特性、職員体制に合った加算を選び、確実に取得することです。
たとえば、昼食提供など食事支援のニーズが高い事業所であれば「食事提供体制加算」を、通所に不安を抱える利用者が多い事業所であれば「送迎加算」を優先的に取得するといったように、収益性だけでなく支援の必要性や現場の実情と照らし合わせて導入を検討しましょう。
記録・体制づくりが加算取得のカギ
加算を取得するためには、定められた支援内容や記録の整備が求められます。特に職員の間での情報共有やモニタリング記録、個別支援計画との整合性など、日常的な運営体制の整備が非常に重要です。
そのため、「加算を取る=仕組みを整える」という構図となり、結果として職員の支援スキルやチーム力の向上にも寄与します。

現場で活用されている主な加算の種類と工夫
ここでは、就労継続支援A型・B型の現場で活用されている令和6年度報酬改定に基づいた加算の一部と、それを意識した支援・記録のポイントをご紹介します。
-
【等級区分とは】
一部の加算では、Ⅰ~Ⅵなどの等級区分があります。これは、障がいの程度や支援の必要度に応じて分けられ、数字が大きいほど重度とされます。重度には高単価の加算が適用され、軽度の単価は控えめに設定されています。
A型・B型 共通の加算
福祉専門職員配置等加算(区分:Ⅰ〜Ⅲ)
概要:社会福祉士や精神保健福祉士など、福祉系の国家資格を有する職員を一定数以上配置している場合に算定される加算です。
取得要件:加算区分ごとに異なる配置基準を満たす必要があります。
<区分>
●Ⅰ:常勤資格者を複数名、一定割合以上配置
●Ⅱ:常勤資格者を1名以上配置
●Ⅲ:非常勤や兼務を含めた体制で一定の割合を確保
取得ポイント:採用段階から資格者を確保するとともに、役割分担や支援方針を明文化して運用することで、支援の質が安定します。
重度者支援体制加算(区分:Ⅰ・Ⅱ)
概要:前年度の利用者のうち、障害基礎年金1級を受給している重度障がい者が一定割合以上在籍している場合に算定できる加算です。加えて、支援記録や届出など、制度で定められた体制整備を行っていることが求められます。
取得要件:区分によって異なる基準を満たす必要があります。
<区分>
●Ⅰ:障害基礎年金1級受給者が前年度の利用者の 50%以上
●Ⅱ:障害基礎年金1級受給者が前年度の利用者の 25%以上かつ50%未満
取得ポイント:制度上の要件を満たすだけでなく、重度利用者一人ひとりのニーズに応じた柔軟な支援設計を行い、支援記録を客観的に残すこと、さらに職員全体で情報を共有し共通理解を深めることが、実際の現場で安定的に支援を継続するために重要です。
食事提供体制加算
概要:収入の少ない利用者の食費負担を軽減し、栄養バランスの取れた食事を提供できる体制を整えている場合に算定される加算です。
取得要件:管理栄養士や栄養士による献立であること、摂取量や体重・BMIの記録などが必要です。
取得ポイント:アレルギーや栄養面への配慮、食育的視点の取り入れ、生活習慣の改善を支援します。
送迎加算
概要:利用者が安心して通所を継続できる体制を整えていることが評価されます。
取得要件:週3回以上の送迎を実施していることや、1回の送迎で定員の半分以上もしくは平均10人以上が利用していることが求められます。
取得ポイント:送迎ルートの効率化、車両管理の徹底、安全運転研修の実施、送迎記録の整備を通じて、安全性と継続性を確保することが重要です。
A型限定の加算
賃金向上達成指導員配置加算
概要:利用者の賃金向上を目的とし、専任の指導員を配置した場合に算定できる加算です。
取得要件:専任指導員の配置、賃金向上計画の作成および年次報告の提出、支援体制の整備が求められます。
取得ポイント:営業力の強化や作業工程の見直し、数値データの記録と可視化、成果の報告体制の整備が求められます。
B型限定の加算
目標工賃達成指導員配置加算
概要:利用者の工賃向上を目的に「目標工賃達成指導員」を専任で配置した場合に算定できる加算です。利用者の工賃を国が定める目標水準へ近づける取り組みを推進する事業所を評価します。
取得要件:専任の指導員を配置し、事業所として工賃向上計画を策定して行政に提出することに加え、毎年度の工賃実績や計画達成状況を報告する体制を整えていることが必要です。
取得ポイント:加えて、販路の開拓やECの導入による販売強化、製品やサービスの魅力向上といった工夫を積み重ねることで、安定的に加算を取得しやすくなります。
-
加算の多くは「記録」と「体制の整備」が取得要件となっています。日々の支援記録や職員配置の記録、支援会議の議事録などを継続的に整備しておくことが重要です。
-
定量的なKPI(例:工賃平均、就職者数)と、定性的な記録(例:モニタリングや本人の希望記録)を両立することで、より高い評価につながります。
-
加算の報告様式や提出期限、配分方法などは自治体により異なるため、必ず地域の障害福祉課や指定権者、本部と事前に確認・連携を行うことが必要です。
※本記事の情報は2025年7月時点の報酬制度(令和6年度報酬改定)に基づいています。
報酬改定は3年ごとに実施されるため、2027年度(令和9年度)までは本内容が基本的に有効とされる見込みです。
ただし、加算の細かな要件や金額、実施方法などは、都道府県や年度ごとに変更される可能性があるため、最新情報につきましては自治体や厚生労働省のWEBサイトなどをご確認ください。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
導入時に押さえておきたい加算活用の注意点
加算を有効に活用するには、単に取得を目指すだけでなく、その運用方法や実務との整合性にも十分な配慮が必要です。加算制度は支援の質を高めるための仕組みである一方で、要件の厳格さや記録の整備など、事業所運営に与える影響も小さくありません。
ここでは、導入時に見落としがちな注意点や、運用上の工夫について解説します。
書類整備と実務の一致を徹底する
加算取得には必ず裏付けとなる記録が求められます。形式だけ整えるのではなく、日々の支援実務と記録内容が一致していることが必要です。
制度監査では、記録の内容やタイムスタンプの整合性まで細かくチェックされるケースもあるため、職員への教育やチェック体制の構築が欠かせません。
また、取得した加算の要件を確実に満たし続けるためには、加算ごとに対応する支援内容を明文化し、職員間での共通理解を図ることが不可欠です。月次や週次のミーティングで加算取得状況を確認し、改善が必要な点があれば早期に修正する体制が求められます。加えて、帳票の様式や記入ルールを統一し、チェックリストを用いた運用をすることで記録精度を高める工夫も有効です。

職員教育と役割分担の強化
加算を取得・維持するうえで欠かせないのが、職員への制度理解の浸透と役割分担の明確化です。加算に関連する記録業務や支援内容は一部の職員に偏りがちですが、属人化してしまうと制度対応にリスクが生じます。
そこで、加算ごとに必要な対応をチーム内で共有し、記録作成・モニタリング・外部連携といったタスクを分担する仕組みを整えることが重要です。新人職員への制度研修やOJTを行い、誰もが「制度と現場をつなぐ視点」を持てるようにしましょう。
また、外部講師による制度研修の実施や、第三者による帳票レビューを定期的に行うことで、現場の制度運用レベルを客観的に確認しやすくなります。さらに、研修内容や対応マニュアルを定期的にアップデートし、職員が最新の制度要件に対応できるよう備えておくことも大切です。
やりすぎは逆効果。現場負担とのバランスを意識
加算を多く取得しようとするあまり、職員の負担が増えたり、形骸化した記録が増えてしまっては本末転倒です。あくまで「支援の質を高めるための加算」という本来の目的を忘れず、現場と経営のバランスを見極める視点が重要です。
「どの加算を優先すべきか」「支援と帳票の整合性は保たれているか」といった視点から、定例ミーティングでのチェック体制を組み込むとともに、業務負担の見直しや改善提案ができる風通しの良い組織づくりもあわせて検討するとよいでしょう。

まとめ : 制度を活かして、持続可能な支援体制を築くために
加算制度は、就労継続支援事業所にとって「必要な支援」を「持続可能な形」で行うための後押しとなる仕組みです。制度の目的や趣旨を正しく理解し、現場の支援と制度対応が一致するような体制を構築することで、報酬という形で経営面にも良い循環を生み出します。
特に、制度変更が多い福祉業界においては、制度に対する理解不足や誤った運用が経営リスクにもなりかねません。未経験から事業を始める方にとっても、既に運営している経験者にとっても、加算制度を味方につける視点が、事業の安定と成長に直結するのです。
また、フランチャイズに加盟している場合には、加算制度に関する最新情報の共有や、必要な申請書類の雛形が用意されていることもあり、現場での導入や運用のハードルが大きく下がるかもしれません。制度を正しく理解し活用できる体制づくりをサポートしてくれる存在として、こうした支援体制を活用することも一つの選択肢といえるでしょう。

加算って、なんだか複雑そうなイメージでしたけど、しっかり理解して取り組めば経営の安定にもつながるんですね。

制度を正しく活用することで、利用者への支援も、事業の持続性も、両方にメリットがあります。最初は大変に思えても、一つひとつ丁寧に積み重ねていけば大丈夫です。

 フランチャイズ
フランチャイズ  就労支援
就労支援  運営
運営 
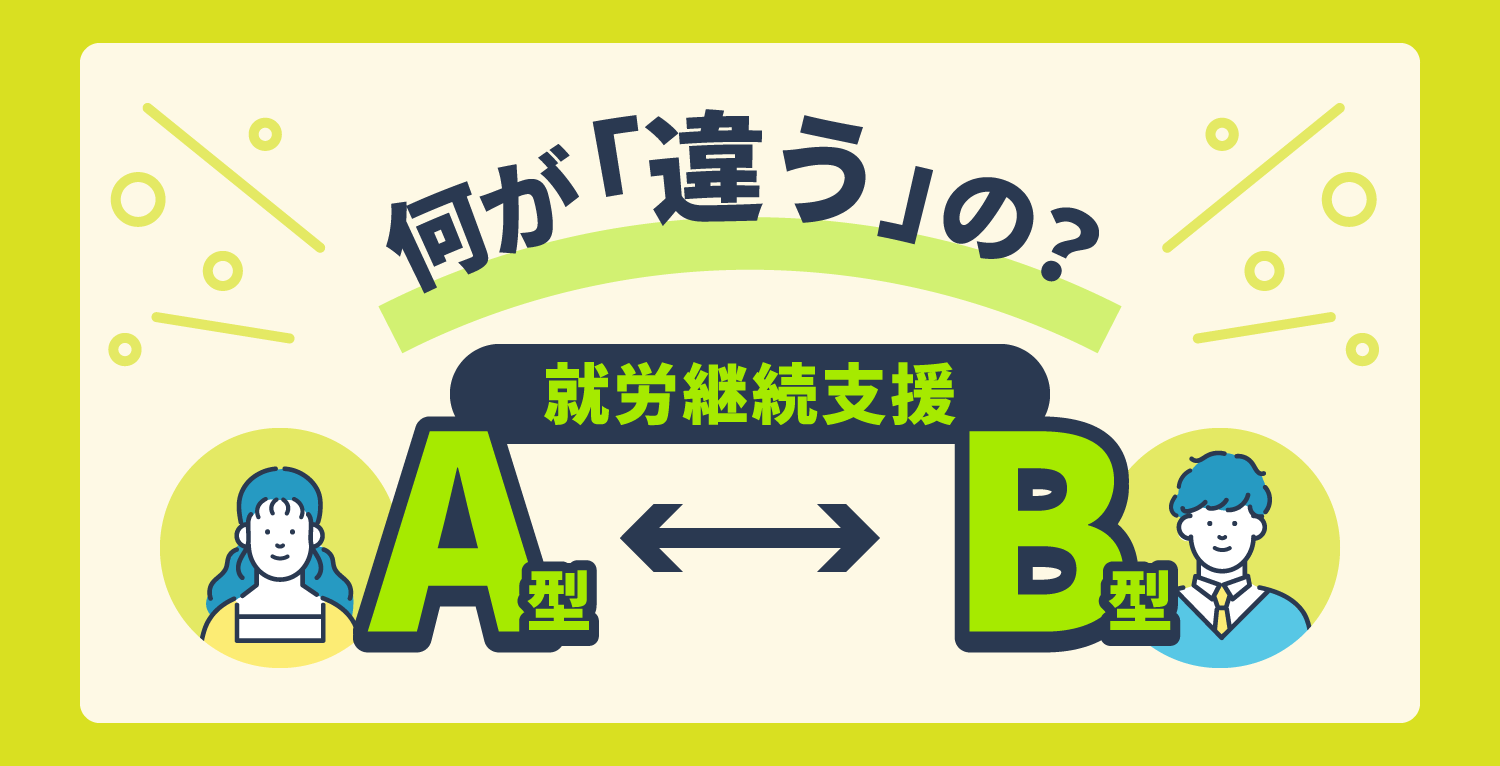


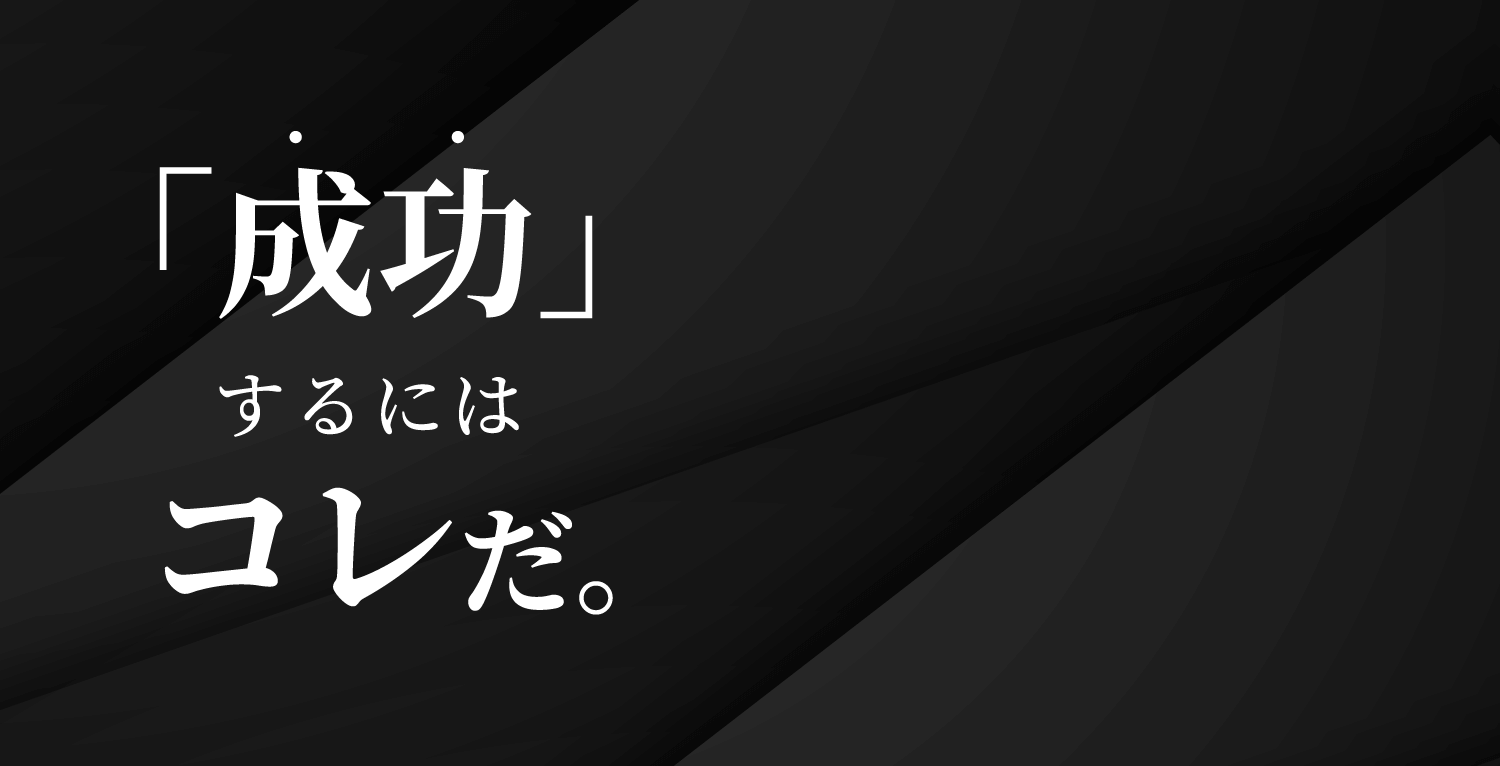

.png)
