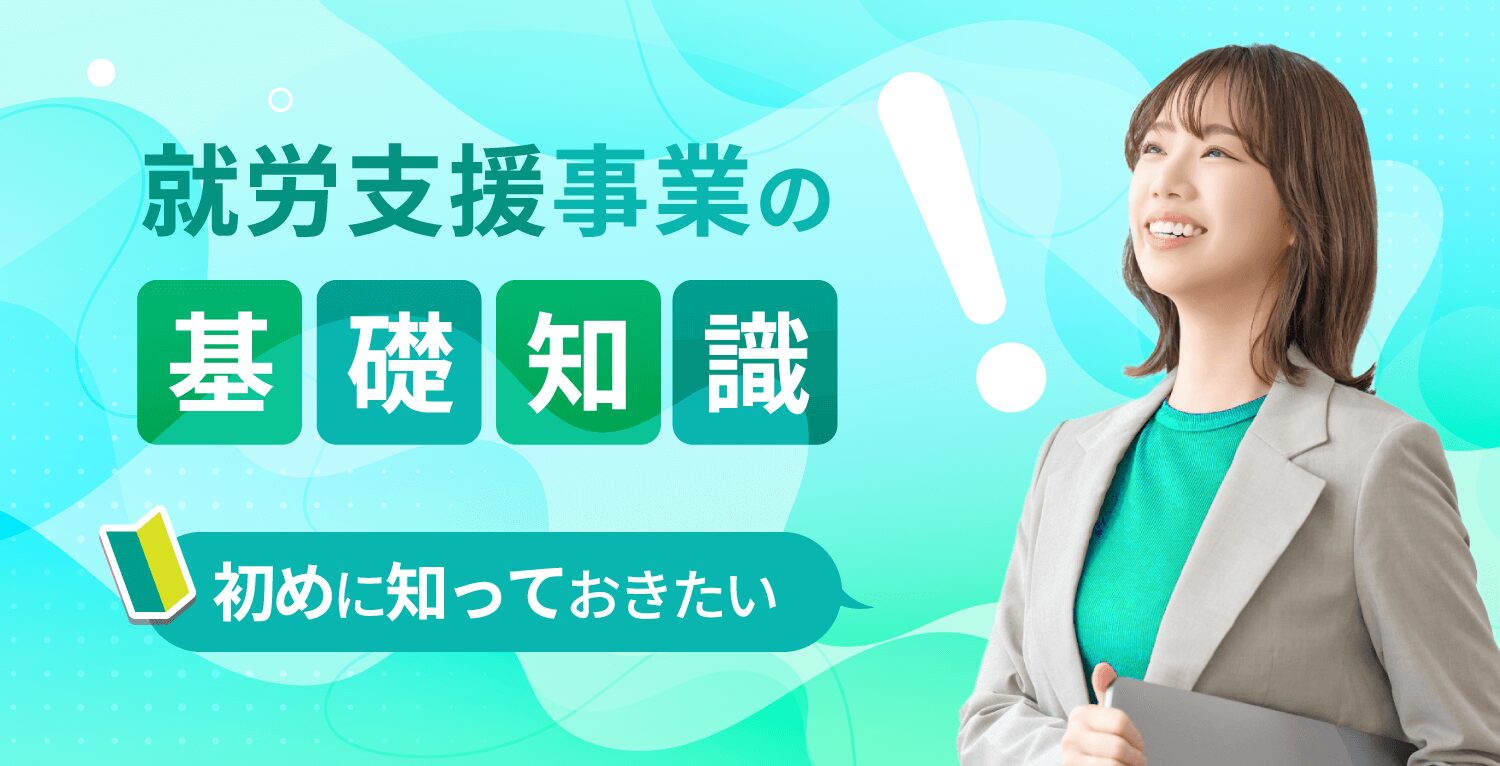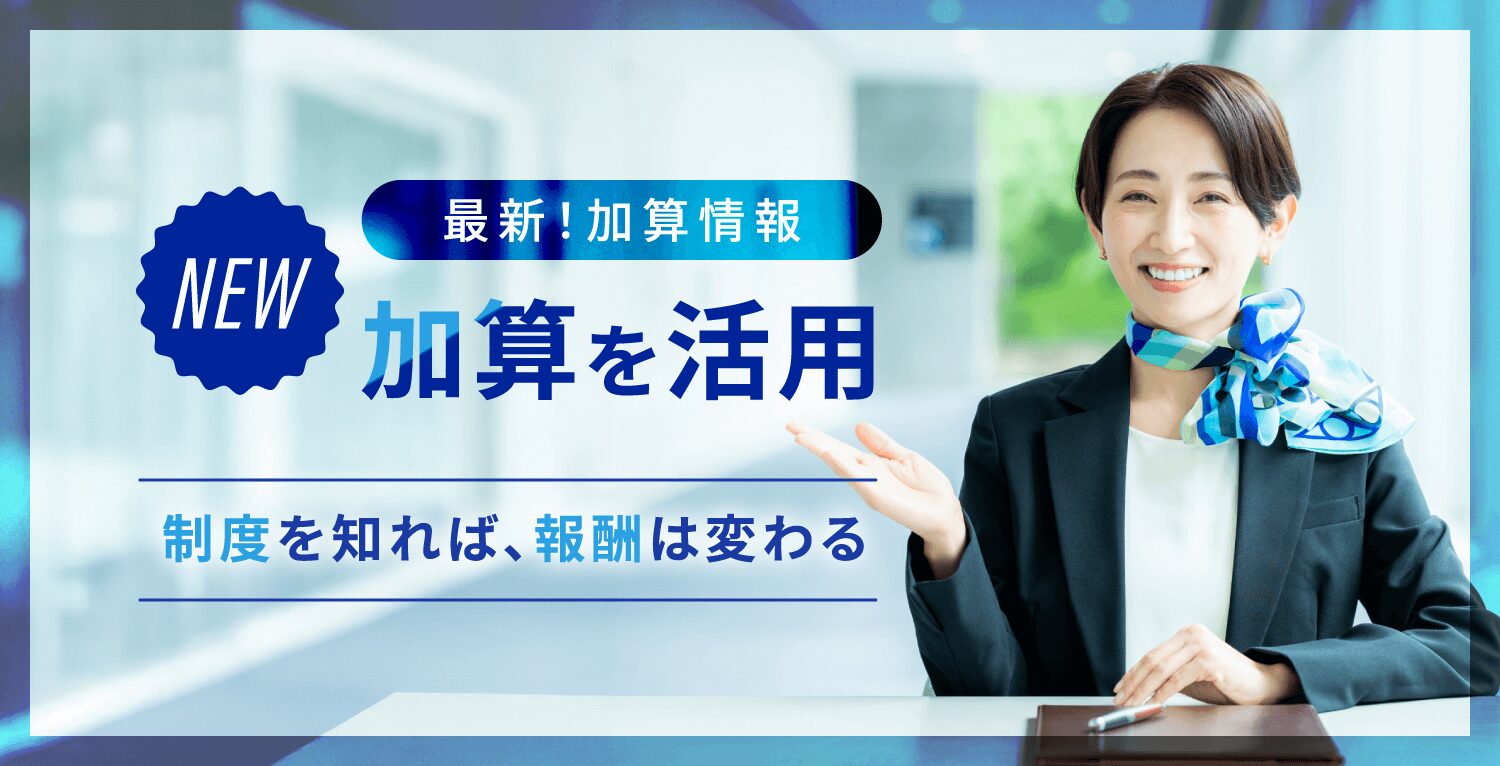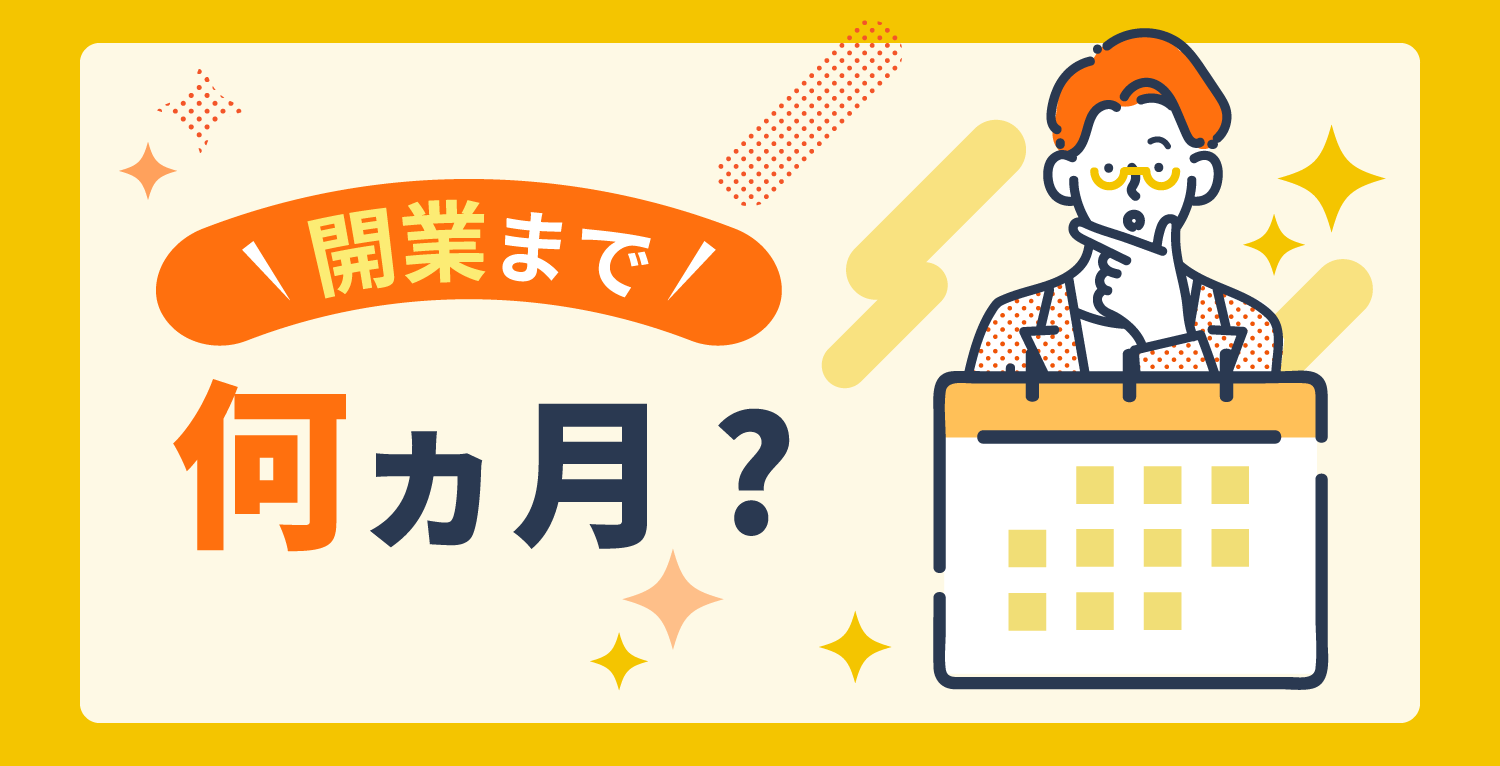なぜ選ばれる?収益性と社会貢献が両立できる就労支援事業の魅力を解説


就労支援には興味があるんですが、正直、収益が出るのか不安で…。

しっかりと仕組みをつくれば、就労支援とビジネスはちゃんと両立できますよ。詳しく見ていきましょう。
福祉の現場というと、「儲からない」「大変そう」というイメージが先行しがちです。しかし、就労支援事業には国の制度に支えられた収益モデルがあり、地域に根ざして長く続けられる仕組みが整っています。
さらに、就労支援サービスを利用する方(以下、利用者)が支援を受けることで成長したり、地域との関わりを持つ機会を得たりすることで、社会にとっても意義のある取り組みとなります。
ここでは、就労支援事業が収益性と社会的意義を両立できる理由をわかりやすく解説します。
就労支援事業は、社会貢献と収益性を両立できる「数少ないビジネス」
就労支援事業は、国の制度によって支えられた収益モデルがあるだけでなく、サービスを必要とする方が幅広く存在することから、地域にとって欠かせないサービスとしての安定性も確保されています。
適切な支援とマネジメントを行うことで、社会に価値を提供しながら、事業としても持続可能な運営が可能です。このように、収益性と社会的意義を両立できる点が、就労支援事業の最大の魅力といえます。
制度とニーズ、両方の「追い風」
「制度によって支えられた収益構造」と「伸び続ける社会的ニーズ」という両方の側面を持つ就労支援事業は、近年ますます注目を集めています。なぜいま、参入の好機とされているのか、その根拠を制度とニーズ、両方の側面から紐解きます。
収益モデルを支える国の制度
就労支援事業は、福祉制度の一環として、国が事業の継続と質の向上を支える仕組みを整えています。その中核をなすのが、利用者支援に対して支払われる「報酬」です。この報酬とは、一般的なビジネスにおける売上や収益にあたるお金です。事業所はこの報酬を基に運営費や人件費をまかない、安定した収益構造を築いています。そのため、一般的な店舗ビジネスのように「売上ゼロ」という状況になりにくいのが特徴です。
具体的には、以下の報酬が事業収益のベースとなります。
● 就労継続支援A型・B型
利用者への支援実績に応じて国から支払われます。
・基本報酬:利用者1人あたりの支援提供日数や時間に応じて支給される報酬
・加算報酬:生産活動の質、一般就労への移行支援体制、個別支援計画の実施状況などに応じて上乗せされる報酬
● 就労移行支援
利用者への支援実績に応じて国から支払われます。特に一般就労への移行実績が重視され、就職に向けた支援内容や成果が報酬に反映されます。
・基本報酬:支援日数や計画実施に基づく報酬(利用者は原則2年間の利用)
・加算報酬:職場実習の実施、一般就労への移行実績、ジョブコーチ的支援の提供などに応じて支給される報酬
制度背景と報酬に関する今後の見通し
障害福祉サービスの報酬制度は、原則3年ごとに見直されます。2024年度の改定では、「生産活動収支」や「一般就労への移行支援」がより重視される傾向が強まりました。これは、事業所自体の経済的な自立と持続可能な運営、そして利用者の待遇の向上、さらに自立支援や社会参加を支える支援が、今まで以上に評価されるようになってきたことを示しています。
こうした背景を受け、たとえば以下のような加算報酬が新設・拡充されています。
【加算報酬例】
●就労継続支援A型 基本報酬におけるスコア方式 区分Ⅱ
生産活動を継続的に黒字で運営できているかどうかが、給付額を左右する重要な要素となりました。
●就労継続支援B型 基本報酬における平均工賃月額 区分
工賃の更なる向上のため、平均工賃が高い区分の報酬単価を引き上げ、低い区分の基本報酬の単価を引き下げる変更が行われました。
●就労継続支援B型 目標工賃達成指導員配置加算/目標工賃達成加算
指導員配置加算の単位数が減額され、達成加算が新設されました。加配そのものへの評価を抑え、実際に工賃を引き上げられたかといった成果・実績に重きを置く評価体系にシフトしています。
生産活動収支を黒字化させることは、就労継続支援事業に義務付けられたものになります。特に最低賃金の支払いが求められるA型にとっては、大きな打撃となっています。一方で、B型の事業所数は増加しており、利用者の獲得が困難なケースも少なくありません。さらに、B型についてもA型と同様に厳格な報酬体系への見直しの可能性も否定できず、生産活動収支の黒字化と事業所としての特色の確立が、今後の運営における最重要課題となっています。
増え続ける社会的ニーズ
厚生労働省の「令和5年障害者雇用状況報告」によると、日本国内の障がい者の数は年々増加傾向にあります。就業意欲があるにもかかわらず、一般企業での就労が難しい方が多く存在しているのです。
実際、障がい者の就業率は、一般の就業率と比較すると依然として低い水準にあります。特に精神障がい者や発達障がい者の就業率はさらに低く、就労支援の必要性が高まっています。
また、厚生労働省が実施した全国調査でも、障害福祉サービスの供給には地域差があることが示されており、特に地方では十分なサービスが届いていないケースも確認されています。
こうした背景から、就労支援事業所のニーズは年々高まっています。障がいのある方が安心して働ける福祉的就労の場を提供することは、個人の自立支援や生活の質向上に直接つながるだけでなく、地域で暮らし続けるための基盤ともなり、地域社会にとっても欠かせないサービスと言えます。このように、就労支援事業は社会課題の解決と事業としての安定性を両立できる分野であり、これが本事業の特徴です。
地域と人を支える就労支援の魅力
就労支援事業の魅力は、収益性だけではなく、「誰かの役に立てる」という明確な社会貢献の性質があることです。
まず、施設を利用する方にとっては、働く経験や職業訓練を通して自立する力を身につけることができます。就労継続支援A型・B型では、実際の作業や生産活動を通じて働く習慣や技能を養います。地域企業との連携や製品販売、軽作業の受託などを経験することで、社会との接点も広がります。また、就労移行支援では、一般企業での就労に向けた職業訓練や職場体験を通じて、実務スキルや生活スキルを高めることができます。こうした取り組みは、本人の自信や意欲を高め、生活全体の安定にもつながります。
一方、地域社会にとっても、就労支援事業は重要な意義を持っています。就労継続支援A型・B型事業所では、利用者が作った製品を地元の商店で販売したり、企業からの軽作業を請け負ったりすることで、地域内で経済的な循環が生まれます。また、就労移行支援を通じて地域の一般企業で利用者が働くことで、地域の労働力不足の解消や経済活動の活性化に直結します。このように、障がいのある方が社会に参加する機会を提供することは、地域全体の福祉環境の底上げにも寄与し、行政や住民との連携を深めることで、事業所は地域にとって欠かせない存在となります。
さらに、事業所で働く職員にとっても大きなやりがいがあります。利用者の成長や社会復帰を間近で支援できることは、働く意義を実感できる貴重な機会です。チームで連携して支援を行うことで、職場の達成感や満足度が高まり、結果として事業全体の質向上にもつながります。

まとめ : 未経験でも挑戦できる「人と社会をつなぐビジネス」
就労支援事業は、「社会に必要とされること」と「収益が見込めること」が両立する、数少ない事業モデルの一つです。制度の後ろ盾、地域ニーズの高まり、支援のやりがいと、どれをとっても今後ますます重要性が増す分野といえるでしょう。
近年では、開業に向けたノウハウやサポート体制が整ったフランチャイズも登場しており、制度対応や人事採用、運営面での不安を軽減しながらスタートできる環境も広がっています。
「一歩踏み出したい」という思いを、確かな仕組みと支援体制でカタチにできる今だからこそ、自分らしい挑戦を始めてみる価値があります。

ちゃんと「仕組み」があるから収益と社会貢献が両立できるんですね。

はい。しっかりとした制度設計があるからこそ、支援の質を高めつつ、経営の安定にもつながります。私たちも、全力でサポートしますよ。

 フランチャイズ
フランチャイズ  就労支援
就労支援  運営
運営 

.jpg)